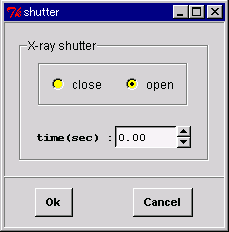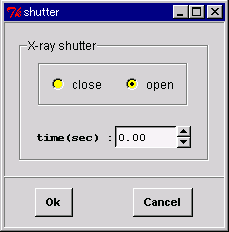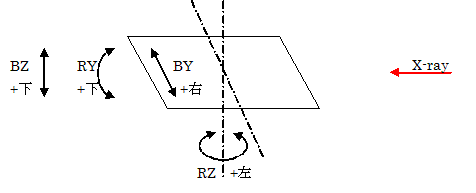実験定盤の調整
1.はじめに
ここでは、実験定盤調整(最適化)を行う。
IC#2(コリメータ直前)での強度が最大になるように調整する。
既に「分光器の調整」と望遠鏡の調整が行われている事を前提に話を進める。
2.調整準備
- "Rapid auto_sp8"を立ち上げ、イニシャライズして下さい。
(すでにイニシャライズしてある場合は1.の操作は不要です)
- 蛍光板をセットします。
(実験ハッチの後ろ側においてあります。)

- モニターを見ながらピントを合わせます。光源(MegaLight50)のスイッチを入れ、光を出します。
- センタリングねじでX線方向に前後に動かし、モニタを見ながらピントを合わせます。
(ピントが合う位置がサンプル位置です)
- サンプル下流に検出器保護用の鉛(白色ランプ)をセットする。

- スリット1のカバーをはずし、スリット1を前開にする。
- IC#1の下流(サンプル側)にアッテネータ(Al : 200um〜1000um)を入れる。(厚さは様子を見ながら調整)
- RaxisVモードにし、カメラ長を300mmにする。
- 定盤にジャッキがかけられている場合は、ジャッキを外す。
- 退出し、ビームを出す。
- 「分光器調整」を行った光が来ていることを確認する。
- IC#2で"Tune"するように、IC#1とIC#2のケーブルを入れ替える。
- "Rapid auto_sp8"からシャッターを開ける。
"Manual"→"X-ray shutter"で以下のウィンドウが開く。
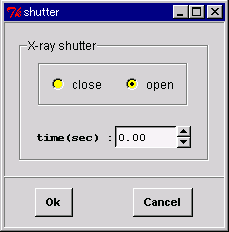
上図の状態でOKを押すとシャッターが開く。
3.調整作業
実験定盤と各軸の関係
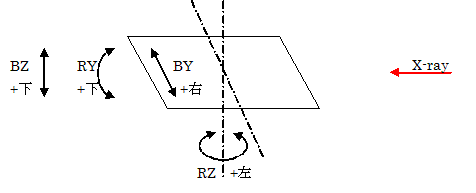
- BY(左右)、BZ(上下)で定盤を動かし、光が蛍光板の中央に来るように大まかに合わせる。
- (光が明るすぎる場合には、アテニュエータを増やす)
- RYを-2000plsする。
- BZを-2000plsし、+200pls動していく。
- RYを+200pls動す。
- 2〜4の操作を繰り返しIC#2が最大となるBZ、RYを探す。
- RZを-200plsする。
- BYを-200plsし、+20pls動していく。
- RZを+20pls動す。
- 6〜8の操作を繰り返し、光が蛍光板の中央にあり、かつIC#2が最大となる様BY、BZ、RY、RZを調整する。
- RY→+1500パルスする。
- マイクロメータをリセットすし、-400になるまでジャッキアップする。
- 光が蛍光板の中央に光があることを確認する。
- "Tune"する。
-
スリット1を0.3mm×0.3mmにする。
-
IC#2が最大となるように、DY、DZを動かす。
-
シャッターを閉める。
-
ビームストッパーを調整する。
2.作業が終わったら
- BY、BZ、RY、RZ、DY、DZ、IC#0、IC#1、IC#2の値をログノートに記録する。
- IC#1で"Tune"するようにケーブル接続を元に戻す。
Home BL45XU-PX TOP BL45PXーGuide