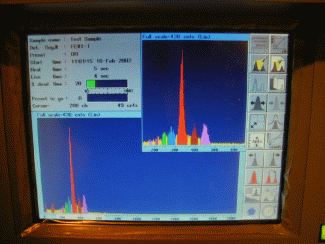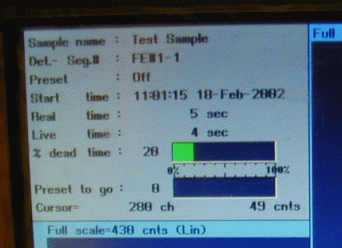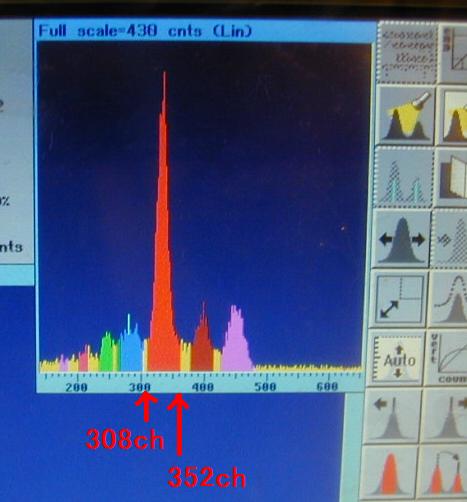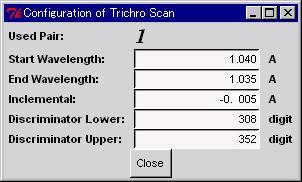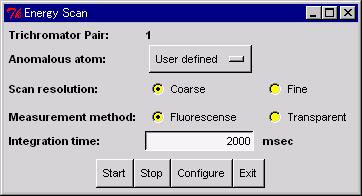Amptekは通常ゴニオメータの奥においてあります。
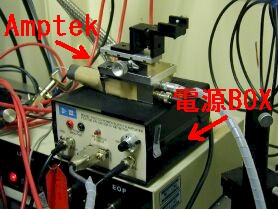
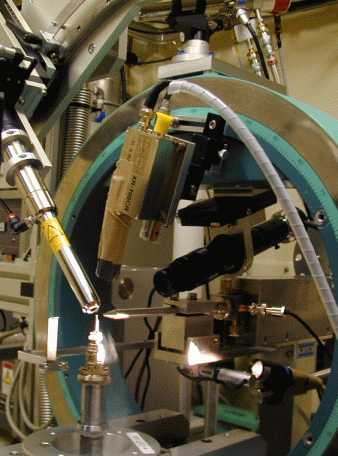
(白色ランプには鉛板が貼ってあります)

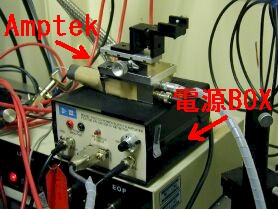
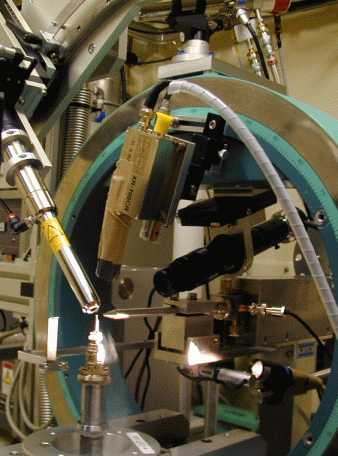

"Trichro"を立ち上げます。
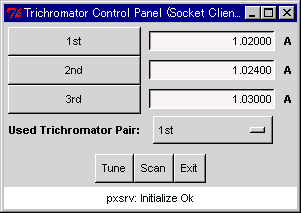
波長を変更する前に、十分な強度が確保できていることを確認します。IC#1ピコアンメータの値が数十nAあれば十分です。無い場合はこちらを参照してください。
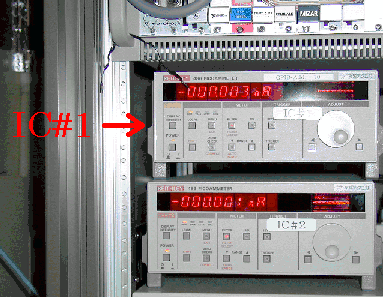
アンジュレータ(挿入光源)のギャップ値を適切な値に変更します。
手順を誤ると、小角散乱ステーションの実験に支障を来すので、事前にGAPの変更についてを確認してください。
波長は1stペアを対照(リモート)に、2ndと3rdペアを吸収端の波長の前後にセット
します。(操作方法はこちら)
このとき、2ndと3rdの波長は2nd<3rdとなるようにしてください。
"Rapid auto_sp8"からシャッターを開けます。
"Manual"→"X-ray shutter"で以下の窓を開きます。
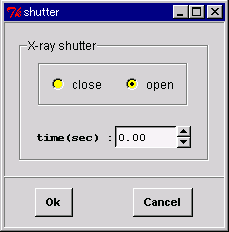
上図の状態でOKを押すとシャッターが開きます。
MCAの"dead time"が10〜40となるように、Ampteckと結晶の距離、
アッテネーターを調節します。
以下の表は目安です。
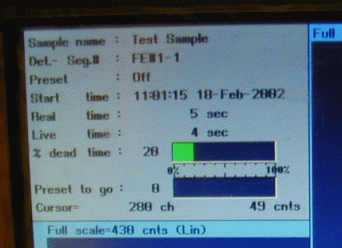
| 波長 | カウント(dead time) |
| ピークより低エネルギー側 | 10〜20 |
| ピークより高エネルギー側 | 30〜40 |
カウントが少ない場合は、結晶が正しくセンタリングできていないか、Ampteckの
向きが結晶を外していて蛍光を拾えていないかが考えられます。また、Ampteckと結晶の距離が不適切なのかもしれません。
カウントが高い場合は、Ampteckを少し遠ざけるか、アッテネーターを挿入してX線の強度を落します。
アッテネーターの挿入には、PC(bl45pxl)のデスクトップの"Attenuator.vi"を立ち上げます。
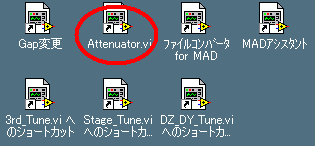
"Filter
Select"から希望のものを選択し、"GO"を押します。
ここで使用するのはAlです。(Au、Pt、ZnはBL調整用です)
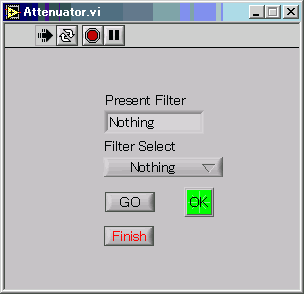
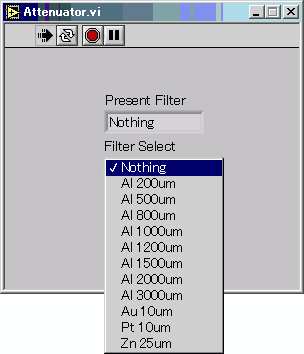
MCAの"dead time"を確認し、必要であれば厚みを変えて下さい。
注意: 測定終了後、アッテネーターは"Nothing"を選択して下さい!!
操作するペアを"Trichro"のメインウィンドウ の"Used Trichromator Pair"から選びます。
"Scan"ボタンを押すと、図のような窓が開きます。
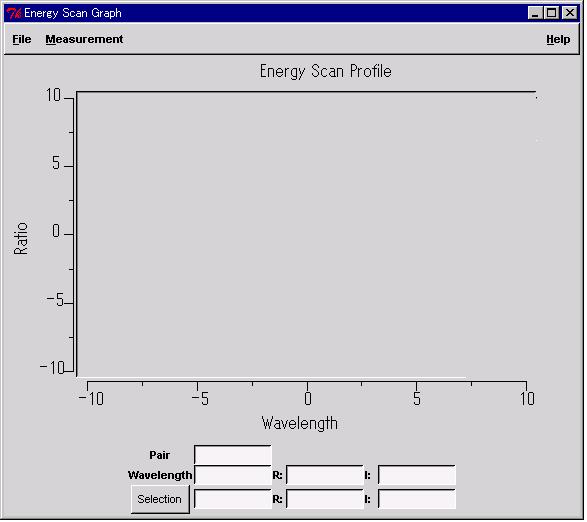
次に、メニューのMeasurementからScanを選んでください。以下のような窓が開きます。
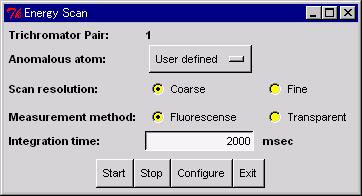
"Anomalous Atom"で核種を選び、スキャンのステップを"fine"(0.0001Aきざみ) か"coarse"(0.0005Aきざみ)で選択し、測定方法を"Fluorescence"にして、"Integration Time"は デフォルトを参考にして適当な値にします。(より詳しい使い方については後述します)
設定できたら"Start"ボタンを押します。保存するファイル名を入力しした後、測定が始まります。
始めは波長変更を行うのでグラフが動きません。フリーズではないので注いして下さい!
測定が始まると、下図のようなグラフが表示されてゆきます。
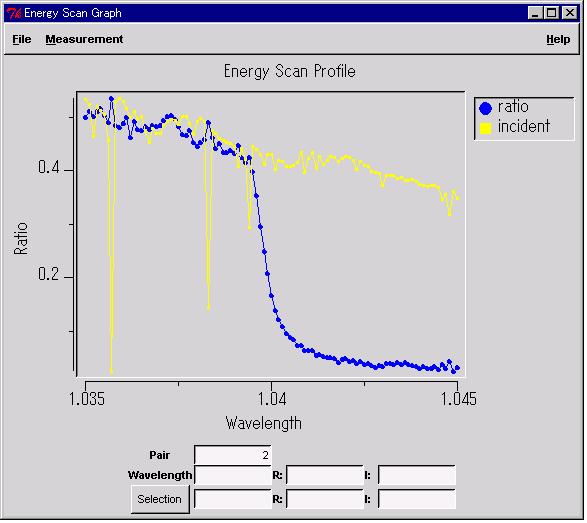
画面を拡大したりしてエッジやピークの波長を確認してください。マウスの中ボタンで、目的の波長のデータ点を中ボタンでクリックすると、グラフの下にある"Selection"の欄に 値が入ります。
"Selection"ボタンを押すと、その波長にセットされます。
この操作を2nd、3rdについて行い、エッジとピーク決定すれば、MAD法のデータ収集の準備は完了です。
念のため、各波長の強度を"Tune"ボタンを押して、調整しておくと良いでしょう。
![]()
"Rapid auto_sp8"からシャッターを開けます。
"Manual"→"X-ray shutter"で以下の窓を開きます。
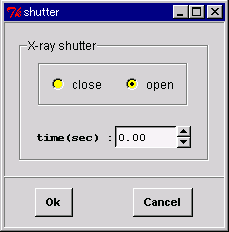
上図の状態でOKを押すとシャッターが開きます。
MCAでスペクトルを見ます。